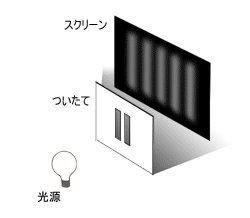
宇宙の秘密 その3
この「宇宙の秘密」と題したエッセイも三回目でございますな。一応今回をもってひとつの区切りとしたいですな。となるとですな、いよいよ量子力学という、過去二回のエッセイでは、なるべく避けてきた理論にも立ち入らなければならないわけですな。
ビコーズ。現代の科学者は、一般相対性理論と量子力学の二つを、基礎的な理論として宇宙を語っているからなんですな。
やれやれ……
正直いって、ぼくには量子力学の解説は荷が重い。いや、不可能とさえ思える。とはいえ、避けて通れる道ではないのなら、ぼくにできる、精一杯の努力をしてみよう。と、そういうわけだから、遠回りで退屈かもしれないけど、ぼくの一番得意な方法を採用させてほしい。
たとえば、そう、紀元前の話からはじめてみるとか……いいよね?
地球が丸いと最初に言ったのはだれだったろう。この手の問いかけに答えを求めるなら、まず古代ギリシアを疑ってみるべきだ。と思って調べてみたら、やはりそうだった。なんと紀元前(以下、BCと書きます)6世紀ごろのギリシアの哲学者たちは、すでに地球は球体だと思っていた。すごいじゃん。
いやいや、早合点しちゃいけない。彼らは理論と観測データから、そう結論したわけじゃないんだ。ハッキリ言っちゃうと、単なる神秘主義。というのはね、古代ギリシア人にとって球体ってのは、完全無欠な固体を意味したんだ。完全なる造形。それは神の創造にほかならないから、地球も球体なのだと結論したわけよ。
そして時は巡り、BC350年ごろに、アリストテレスが登場した。古代ギリシアのアテネは三人の有名な哲学者を輩出した。ソクラテス、プラトン、アリストテレスだ。ソクラテスは気のいいオッサンで、道徳を説いて回った。ソクラテスの弟子がプラトンだった。彼は、この世はすべて、イデアという、あの世だかなんだかわからん世界の影にすぎないと主張した。いいとこの坊ちゃんで、美男子だったそうだけど、かなり電波系。友だちにはしたくないタイプかも。そして、そのプラトンの弟子がアリストテレスだった。アリストテレスは、師匠とは正反対に、この目で見えるものを信じた。プラトンの弟子だけあって、形而上学なんか作ったけど、経験を重んじるオッサンだった。ぼくが調べた限りでは、地球が球体だという事実を、はじめて客観的事実から説明したのは彼だと思う。
アリストテレスの論拠は単純明解だ。
証明1
彼はまず、星に注目した。もしも地表が平らだとすれば、地表のどの位置からも、同じ星が見えるはずだ。ところが、旅行者が南に行くにつれ、いままで見えていた星が、北の地平線に隠れてしまい、こんどは、いままで見えていなかった星が、南の地平線から現れる。これは、地表が曲面であると考えなければ、説明がつかない現象だった。
証明2
つぎに彼は、陸地から離れていく船に注目した。船は水平線に近づくにつれ、徐々に沈んでいくように見える。ところが船は沈んだわけではなく、ちゃんと帰ってくる。こんどは海からせり上がってくるように見えながら。これも地表が曲面だと考えれば説明がつく。(余談だけど、当時はいかに空気が澄んでいて、いかに人々の目がよかったかという証明だよな、この話は)
証明3
まだある。アリストテレスの時代にも、月が地球の影に入ったときに、月食が起こることが知られていた。つまり、月に落ちる影は、地球の形だ。ここまでいえばわかると思うけど、だれが見ても、その形は曲がっていた。そういう影を落とすためには、地球が球体でなければ説明がつかなかった。
どうよ、わかりやすいじゃん。
以上の三つの証拠から、アリストテレスは地球が球体だと主張した。彼の考えはじつにわかりやすくて説得力があったから、みんな気に入った。だから、その後の歴史を通じて、アリストテレスの著書に触れたことのある教養人のほとんどが、地球が丸いことを認めたんだよ。となると、コロンブスが地球は丸いと信じていたのも、べつに驚くべきことではないよね。それどころか、じつはコロンブスの計画を採用しなかったポルトガルの学者も、地球は丸いと知っていたんだよ。
ところがどっこい、アリストテレスほどの知性があっても、大きな間違いをおかすことがある。彼は、地球が宇宙の中心だと信じていたんだ。彼の時代以前にも、早くも太陽中心説を唱える哲学者がいた。でもね、アリストテレスは見事な弁論によって、太陽中心説を唱える連中を笑い飛ばしたんだ。笑い飛ばされた初期の哲学者の中には、アリストテレスに笑われたからこそ、名前が残ってる人もいるぐらいだ。
でもって、アリストテレスのオッサンが世を去ってしばらくして、サモアのアリスタルコスが登場した。このオッサンが、古代における太陽中心説の主役だ。彼の着眼点は、なかなかいい線いってる。かなり論理的で説得力がある。でも残念ながら、すでにアリストテレスの宇宙観が支配的な時代にあって、アリスタルコスの主張が受け入れたれることはなかったんだ。
そうはいっても、いつの時代でも、第一級の頭脳を持った人々は、アリストテレスの誤りに気づいていた。アリストテレスはおかしいぜ。間違ってやがるんじゃないか?
ところが、そのだれもが、アリストテレスの宇宙観を破壊するほど、説得力のある説明や決定的な証拠を示せなかったので、われわれは1543年の、ニコラス・コペルニクスの書物が出版されるまで待たなくてはならなかったんだ。彼は、その書物の中でアリスタルコスの考えに立ち戻り、過去や未来の惑星の運行を計算するには、地球が動いている(というか、太陽が中心にある)と考えるほうが計算が楽だと指摘した。
楽なほうがいいじゃん! 変な計算をこねくりまわして、無理やり地球が中心だと考えるのはよそうぜ!
なーんて、言ったら、あんた大変ですよ。その当時は、異端審問所って怖い場所があったからね。知ってる? イタリアの学者だったジョルダノ・ブルーノなんか、太陽はほかの星と一緒で、べつにたいしたもんじゃないぜと言って、火あぶりにあって殺されちゃったんだぜ。黙ってりゃよかったのに。彼の前に、ドイツの学者で、しかも驚くことに聖職者だったニコラウスが同じことを言ったけど、ニコラウスは才覚があって思慮深かったから、枢機卿として有徳のうちに、ベッドで安らかに死んだ。うまいやり方だ。
さて。コペルニクスが太陽中心説を示唆した1543年という年は、じつはコペルニクスが世を去った年なんだ。いやいや、ご安心めされよ。コペルニクスは火あぶりにあって死んだんじゃないんだ。ちゃんと自分の家の畳の上で…… いや、ベッドで死んだ。というのは、異端審問所にとっ捕まって、火あぶりにされるのがわかってたから、彼は、自分がベッドの上で、安らかに死を迎えたあとに研究結果を発表するようにと、友人に書物の出版を託して死んだんだ。いまの時代じゃ考えられんぜ。いまの科学者は、自分の研究成果を自由に発表できる。というか、発表したくてしょうがない(企業や政府の秘密の研究に関わっているんでもないかぎりだけど)。だって、ノーベル賞をもらえるかもしれないもんね。
ところが、コペルニクスの時代には、そういう満足感を味わうことはできなかった。科学に携わっていれば、いやでも神の否定にならざるを得ないところがあるから、正直なヤツは、みーんな火あぶりで殺されちゃう。ヤバイ時代だ。
だからコペルニクスは、念には念を入れて、最初の原稿には書いてあったアリスタルコスの名を削除しておいた。アリスタルコスの考えを復活させたとなると、世間の反発は、よりいっそう激しいものになると予測したからだね。それでも、コペルニクスの説は、反論の余地がまったくないほど決定的ではなかったので、数学的技巧として、あっさり片づけられてしまった。
つぎに注目すべきは、イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイだ。彼は、簡単な望遠鏡を組み立てて、それを1609年に空に向けた。その結果、ついに太陽中心説は、反論の余地のないものになった。いまの時代より、夜空はずっと暗く(街の明かりがない)、さらに澄んでいたとはいえ、よくもまあ、粗末な望遠鏡で調べたもんだよ。
もちろん、ガリレオも無事じゃなかった。みなさんもご存じのとおり、異端審問所に呼び出され(怖いよ〜)、こっぴどく怒られたあと、太陽中心説は、ただの冗談だったと表明するか、あるいは火あぶりで命を落とすかの選択を迫られた。彼は冗談で済ますほうを選んだ。当たり前だ。そんなことで死んでられるかよ。しかも焼き肉にされるんだぜ。冗談じゃない。ただ、伝説によれば、異端審問所を出るときに「それでも地球は回っている」とつぶやいたそうだ。まあ、単なる伝説だろうけど、カッコいいよね。
じつは、まったく同じ年の1609年に、ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーが、惑星の軌道は楕円であると主張していた。この話も書きたいと思う強い衝動を感じるけど、エッセイの論点がズレすぎるので、今回は我慢しよう。
さてさて。ガリレオくんに戻ろう。彼は天体の観測だけでなく、もう一つ、後世に多大な影響を残すことになる重大な実験を行っていた。それは落体の実験だった。アリストテレスは、じつはもう一つ、どえらい間違いをおかしていた。彼は重い物のほうが、速く落下すると主張していたのだ。これは、とんでもない間違いで、しかも、実際に実験するまでもなく、簡単な思考実験で間違いに気づくことができるんだけど、なぜか世間は2000年近くもアリストテレスの「間違った考え」を信じていた。
で、われらがガリレオくんは、こちらも疑問の余地なく正しい考え方を世間に提供した。重い物も軽い物も、同時に落ちるんだとね。伝説によると、ピサの斜塔で実験したことになっているけど、そんな事実はなかったって、みんな言ってるよ。(実際には、ゆるやかな斜面を作って、そこに丸い玉を転がして実験した)
こうして、いよいよニュートンが登場する。
ニュートンは、ガリレオの落体の実験をもとに、運動の法則を作り出した。彼はまぎれもない天才だった。リンゴが落ちるのを見て、じつは「月も落ちてるんじゃないか」と考えたんだ。ふつう、そんな発想しないよ。天才は違うねえ。
それにしても、万有引力の法則ってヤツはすごい。感動するよ。厳密な計算を必要とする場合は、アインシュタインの一般相対論が必要だけど、そうでない場合は、ニュートンの法則は、いま現在も十分に通用するんだ。だいたい、ニュートンの方程式には、アインシュタインの方程式にはない優れた利点がある。彼の用いた数式は、ぼくでさえ理解できるほどに簡単なんだよ! すばらしい!
まあ、それはともかくとして。
アリストテレスと、ニュートン(ガリレオも含む)の考えの違いはなんだろう。それは、アリストテレスが、地球が「静止」していると信じていたところだ。ところが、ニュートンの法則からいえば、静止の特別な基準はない。
前回のエッセイで書いた、電車に乗った人がコップを落とすところを思い出してほしい。繰り返しになるけど、もう一度書こう。
あなたはいま、一定のスピードで動いている電車に乗っている。この電車は、すごく性能がよくて、振動もしないし風を切る音もしないし、窓も閉まっているから、あなたにとって、動いているのか静止しているのかわからない。
そこであなたは、手に持ったコップを、そっと離して電車の床に落としたとしよう。すると、コップはあなたの足元に落ちる。コップの落ちる前と落ちたあとの位置は、高さが違うだけで、水平には動いていない。
ところが、その様子を外で眺めている人がいたとしよう。あなたがコップを離した瞬間、その人の前を通りすぎたとすると、その人にとって、コップが落ちた位置は、電車が動いた分だけ、水平に移動しているはずだ。
あなたは、コップが水平に移動したとは思えない。ところが、外にいる人は、コップが水平に移動したように見える。どちらが正しいのだろう? じつは、それを決定する方法はない。どちらか一方の見方を、他方の見方より優先させる理由はないんだ。
もちろんニュートンが、このことに気づかないわけがない。だから彼は大きなジレンマに陥った。絶対的な位置が存在しないことを認めるのは、彼の宗教観が許さなかったんだ。なんと、ニュートン先生ってば、神さまを信じてた! この宇宙の現象は、一番最初に、神さまがネジを巻いて、それが時計のように正確に時を刻んで進行している姿だって思ってたんだ。ホントかよ? あのニュートンが? 本当なんだ。
余談だけど、そういう考えをむちゃくちゃ信じていたので有名なのが、フランスの数学者ピエール・シモン・ラプラスだった。ラプラスはニュートンの考えをもっと進めて、時の始まりの全原子の初期運動がわかっていれば、未来のあらゆる出来事を計算できると考えた。彼の言う「計算できる未来」には、あなたが、十年後にどのレストランで、どんな料理を食べるのかということまで含まれていた。こういう考え方を「決定論」と言うんだ。なにもかも、「決定」できるから。しかし、ラプラスってば、メートル法の制定にも参加した人なんだけどねえ。ちょっと電波を受信しちゃったのかも。
まあ、ラプラスまで極端じゃなかったけど、ニュートンが、絶対的な位置が存在しないことを、自身の法則が示しているにもかかわらず、それを認めるのを渋ったのは事実なんだ。彼のような天才でさえ、われわれが日常的に感じる常識的なものの見方から(宗教観が邪魔をしたとはいえ)、思考を飛躍させることができなかったね。その点で彼は、アリストテレスと同じ過ちを犯したといえる。皮肉な話だ。
ま、ニュートンが望まない結果だったとはいえ、彼のおかげで、空間内の絶対的な位置という概念は壊れてしまった。そのことを、ハッキリと世に示したのはアインシュタインだった。彼は空間だけでなく、時間も絶対的ではないと主張した。つまり、ニュートンの法則から導かれることだけでなく、それをさらに拡張したのだよ。
またまた繰り返しになるけど、アインシュタインも振り返ってみよう。
アインシュタインは、マックスウェルの電磁波の方程式から、光速は一定であって、どんな条件でも変化しないと仮定するところからはじめた(アインシュタイン自身、特殊相対論の着想は、マックスウェルの方程式のおかげだと言ってる)。もちろんマックスウェルも、自分の方程式を解くと、そういう結果になるのはわかっていたけど、その点に関しては、あんまり深く追求しなかったんだ。
それから半世紀。アインシュタインは光速が一定だと仮定したもんだから、特殊相対性理論は、えらく不思議なものになっちゃった。だって、時間の進み方が遅くなるんだよ。信じられる?
よし。いま仮に、光のスピードが101キロだとしよう。で、あなたは100キロのスピードで進むロケットに乗って、その光と並んで飛んだとしよう。あなたは、光のスピードが何キロに感じるだろう? 答えは簡単。スピードの差は1キロだから、当然1キロだ。光は、1キロのスピードで、あなたのロケットを追い越していく……
ちがいまーす。そんな答えをテストに書いたら落第だよ。驚いちゃいけない。あなたは、光より1キロしか遅くないのに、なぜか光を101キロだと感じてしまうんだ。
ハワイ? なぜ? なぜゆえに?
だって、光のスピードは、いつだって一定なんだからしょうがないじゃん。以上説明終わり。なーんて言ったら殴られちゃうな(笑)。いやでも、半分はそうなんだ。光のスピードが一定であるという現象が事実ならば、そのほかの現象をそれに矛盾しないように理論を組み立てなくちゃいけない。だからね、あなたと光のスピードが1キロしか差がなくても、あなたが、光は光のスピードのままだと感じるためには、時計の進み方を遅くするしかないんだ。つまりあなたは、外にいる人から見たら、ビデオをスロー再生したような世界にいるわけ。(前回も、こう説明すればよかったと、少し反省してる)
そんなバカな!
と思うかもしれないけど、理論はそう結論するし、観測したデータは、そのとおりになるんだよ。たとえば、ほんの一瞬しか存在できなくて、観測不可能に思える素粒子も、光速に近づくことで寿命が延びる。だからぼくらは、そういう素粒子も捕まえることが出来るんだよ。つまり、特殊相対論は正しい。以上説明終わり(笑)。
まだ納得できないかな? ふむ。納得できなくても当然だよね。時間が遅くなるなんて現象は、ぼくらの生きている世界では起こらない。なにせ、頭のいい科学者のみなさんだって、アインシュタインにそんなこと言われてって信じられなかったんだ。だいたい、当時のアインシュタインは、スイスの特許局で働いてる無名の二十六歳の若造だったから、なおさらだよ。彼の理論に注目したのは、ほんの少数だった。
ところで、アインシュタインは、特殊相対論を発表する数週間前に、光電効果の論文を発表している。彼に先立つこと五年前、マックス・プランクが、黒体輻射の現象を説明するのに「量子」という考えを提唱したけど、アインシュタインは、プランクよりも量子の重要性に気づいていた。
つまりアインシュタインは、光電効果ではプランクの、特殊相対論ではマックスウェルの方程式に隠された謎の重要性にも彼は気づいていたわけ。彼は、特許局で働いてたおかげで、だれかの理論から、重要な論点を探し出すのがうまくなったのかもね。なにせ、わけのわからない発明が本物かニセモノか、見抜かなきゃいけなかったからねえ。
ところが!
そのアインシュタインでさえも、古くはアリストテレスが、そしてニュートンがおかしたのと同じ過ちをおかそうとしていた! ニュートンは、自分の理論から推論される結果を認められなかった。アインシュタインも、自分が扉を開けた量子論から推論される結果を認めることができなかったんだ。
さーて。そんなわけで、そろそろ、やりますか、量子論。
この科学エッセイでは、いままで何度も量子論という言葉を使っているけど、一般的にはあまりなじみがないかもしれないね。ぼくの勝手な印象だけど、自然科学の重大な理論の中で、一般にもなじみ深く、よく知られているのはダーウィンの「進化論」ではないだろうか? そのつぎが、ニュートンの万有引力の法則かな。そして、メンデルの遺伝の法則やフロイトの夢判断などが続いて、アインシュタインの相対論(アインシュタインを知らない人はいないだろうけど)は、かなり知名度が落ちて、量子論に至っては、名前すら知らない人が多いような気がする。
でもね。われわれは、上にあげた理論の中では、量子力学からの恩恵を一番受けているんだよ。テレビだって量子力学がなければ発明されなかったし、いま、あなたがこのエッセイを読んでいるだろう、コンピュータも量子力学の産物だ。それどころか、量子力学の範囲は工学に留まらない。いまや生物学にも量子力学は欠かせない。たとえはDNAを解析する方法とかね。量子力学なんか知らなくても生きてはいけるけど、知っていても損はないよ。だから、この先を読んでくれるとうれしいな。
そうそう。量子力学は役者が多いんだ。そうだな、相対論はマラソンに似てるかもしれない。たくさんの走者がいたけど、スタートを最初に切ったのはアインシュタインで、彼は常に相対論のトップランナーであり続け、ゴールに最初に飛び込んだのもアインシュタインだった。ところが、量子論はサッカーに似てるかもしれない。団体競技だ。敵のゴールに果敢に攻めるたのが、ハイゼンベルクとシュレーディンガーだとすれば、中盤の守りをキッチリ固めたのが、ディラックとファインマン。そして、ゴールキーパーには、ボーアがいた。そんな感じかな。
ではでは、彼らの歴史を語ろう。そのためには、特殊相対論が発表される20年前に戻らないといけない。
量子力学における、最初の一歩は、じつは一人のアマチュア学者が印した。それはバルマーというスイス人の教師だった。バルマーさんには申し訳ないんだけど、ぼくは彼のフルネームも、なんの教師だったかも(体育じゃないと思うけど)知らない。知ってる人がいたら教えてね。そりゃそうと、アマチュア学者というのは現代でも、けっこういるらしいね。その昔は、プロとアマチュアの学者を明確に分けるのは困難だった。たとえば、フランクリンは、雷が電気でできてると証明して、避雷針を作ったけど(凧を使った実験を知ってるだろ?)、この人は印刷業で儲けた実業家で、その後、政治家としてアメリカの独立に奔走して、合衆国憲法を作るのにも参加してる。彼の人生は、政治家として語るべきであって、つまり学者としてはアマチュアだった。
ところが現代は、日曜大工の店でも買えるような、簡単な器具の組み合わせで重大な科学的発見ができるような時代じゃない。何百億円もする、高価な実験装置を使わなければならないことが多いんだ。だから、アマチュア学者の出番はほとんどない。たまに彗星や小惑星を見つけるぐらいだな。
失礼。バルマーに戻ろう。
バルマーは、アマチュアとしては、極めつけの幸運を手にした。1885年に、水素からのスペクトル線に思いを巡らせているうちに、振動数の間に不連続性を発見したんだ。当時の物理学では(現在では古典物理学と呼ばれている)、現象はなめらかに連続していると考えるのがふつうだったから、バルマーの発見は、たしかに不思議な現象だった。とはいえ、古典物理学でも、振動問題に関しては、若干の例外を認めることもあるので、バルマーの発見が、ただちに、古典物理学を揺るがすような問題とは考えられなかった。なにか解決する方法があるはずだ……
なんて思ってるうちに、だれも解決方法を思いつかないまま12年も経っちゃった。
1897年。イギリスの物理学者ジョセフ・ジョン・トムソンが、原子の中に負の電荷を持つ粒子を発見した。それは「電子」と名づけられた。トムソンは、負の電荷を打ち消すために、原子はプラムプリンのような形をしていると考えた。原子には、正の電荷がプリンのように詰まっていて、負の電荷の「電子」は、その正の電荷の中に浮く「干しぶどう」のようなものだと考えたんだ。そうすると、正の電荷に応じて電子は振動するはずだから、バルマーの発見した不思議な現象を解決できると考えた。
ダメだった。そんな理論では、バルマーの発見した不連続性は説明できなかった。
そして……
1898年から1899年にかけて、レーリーとジーンズという二人のイギリスの物理学者が「黒体輻射」について考えはじめたあたりから、いよいよ状況は悪くなってきた。
ところで、黒体輻射を、むちゃくちゃ簡単に言うと、鉄の棒を熱すると、まず赤く光るようになるよね。さらに温度を上げると光の色は、だんだん白っぽくなる。当時、光は「波」だと思われていたから、赤熱したり白熱したりする理由がわからなかったんだ。というのは、光が純粋な波動だとすると、赤熱や白熱を説明するためには、光の放射が無限大のエネルギーを持つことになってしまうんだ(なんでそうなるかの正確な説明はぼくには出来ないけど)、いうまでもなく「無限大」というのはあり得ないから、こいつは、非常に困ったことだった。
というわけで、約一年後にマックス・プランクが登場する。レーリーとジーンズは、エネルギーは連続していると考えたから、無限大なんてヤバイ結果になってしまったと、プランクは思った。つまり、エネルギーを不連続な塊と考えれば、黒体輻射の問題は解決できると主張した。これも、むちゃくちゃ簡単に言うと、こういうことだ。光は波動なんだけど、その波動を細かく切り刻むことができる。ものすごく細かく切り刻めば、それは一個の粒子と同じ振る舞いをするんじゃなかろうか? プランクは、この「細かく切り刻む」という考え方を「量子」と呼ぶことにした。でもプランクは内気な男だったから、最初は自分の発見に自身が持てなかった。実際、世間の目は冷たかった。ほとんどの学者は、プランクの考えに激しい疑いを持ったんだ。
ところが。プランクの考えを正しく理解した男がいた。それがアインシュタインだ。彼はプランクよりも早く、量子という概念の重要性に気づき、その理論を使って1905年に光電効果を説明する理論を発表した。特殊相対論を発表する、数週間前だった。
待った。光電効果とはなんだ? うーむ。簡単に言うと、光を物質の面に照射したとき、その面から電子が外部に放出される現象のことだよ。光が波動だとすると、そういう効果は起こらないはずだった。では、アインシュタインは光電効果をどう説明したんだろう?
まず、物質をビリヤードの台と考えてみよう。そこにはいろいろな色の玉が点在している。ビリヤードは、白い玉をキューという棒で打って、色の玉に当てて、穴に落とすゲームだ。つまり、光はビリヤードの白い玉で、中に詰まった電子が、落とされるべき色のついた玉なんだ。そう。光は粒子として、中の電子にぶち当たり、電子をはね飛ばしていたんだよ。波動であるはずの光を粒子と考えるには、量子という考え方が不可欠だったんだ。
この説明によって、光は「波」でもあり「粒子」でもあることが確定的になったけど、光が「波であり粒子でもある」というのは、依然としてパラドックスには違いなかった。しかし、それが現実ならば、なにか理論的に、じつは「パラドックスではない」のだと説明できるはずだ。ところが、アインシュタインには、それができなかった。
こうして徐々に、古典物理学が崩壊していく音が、大きく聞こえてくるようになったけれど、それが決定的になったのが、ラザフォードの研究だった。
ニュージーランドで生まれたイギリスの物理学者アーネスト・ラザフォードは、1911年に、分裂する放射性物質を使って実験を繰り返した結果、原子には原子核があることを決定的に世に示した。電子を発見したトムソンは、原子はプラムプリンみたいだと考えたけど、じつは違っていたわけだ。原子は中心に太陽があり、その周りを地球が回っているような、太陽系に似ていた。(原子核は太陽のように大きくはないけど、まあ、イメージとしてね)
この発見は、それまでの物理学にとって、非常に具合が悪かった。電子が原子核の周りを飛んでいるとしたら、電子は常に飛ぶ方向が変わっているわけだ。方向の変化は、つまり加速と同じだから、エネルギーを失うはずだった。その失ったエネルギーが電磁波として放出される。
とすると……
電子はどんどんエネルギーを失い、しまいには原子核の中に落ちて、その原子は崩壊するはずだ。ところが、たいていの原子は安定していた。たとえば水素原子は、自然に崩壊して消えてなくなるなんてことはないように思えた。原子が安定している以上、それまでの物理学のほうが間違っているとしか思えない。では、新しい理論とはどんなものなんだろう? これからは、それまでの物理学を「古典物理学」と呼ぶことにしよう。
新しい理論の構築に最初に挑んだのは、デンマーク人の物理学者ニールス・ボーアだった。ボーアは1912年に、マンチェスター大学で原子核を研究していたラザフォードのもとを訪れて研究をした。当時27才。ちなみにラザフォードは41才。
ボーアは条件を簡単にするために、電子が原子核を回る軌道を「円」だけに限定することにした。実際には、どんな楕円軌道も考えられるんだけど、混乱したときには円の持つ魅惑的な単純さには抗しがたい。そして一年後の1913年。ボーアは、プランクの量子論を利用して、とびとびの軌道にだけ、電子が存在するような、奇妙な数式を編み出した。結果は大成功。彼の数式は、古くはバルマーが発見したエネルギーの不連続性も、ラザフォードの発見した電子の加速もうまく説明できた。(ボーアはその後、1921年に、元素の周期律の理論を作り出して、1922年にノーベル賞をもらった)
でも……
ボーアの数式は、新理論とはいえなかった。古典物理学をなんとか適当にいじくり回して出来た、不格好な粘土細工みたいなシロモノだった。たしかに水素原子のように、電子が一個しか回っていない場合は、非常にうまいこと計算できる。でも、もっと複雑な原子に対してはどうか? まあ、少しは一般化することが出来そうだったけど、そういう広範囲な現象を説明することは出来なかった。
その後、大きな前進があった。1923年に、フランスのルイ・ド・ブロイが、純粋な粒子だと思われていた電子も、波動と見なすやり方を提唱したんだ。彼の考えは、電子にも回折現象があることが発見されて証明された。
さらーに、1925年。オーストリアの物理学者ヴォルフガング・パウリが、二つの同じような粒子は、同じ状態を取ることができないことを発見した。これはパウリの排他原理と呼ばれている。(この原理を説明するには、粒子のスピンを理解しなきゃいけないので、ここでは割愛するよ)
光だけじゃなく、電子にも粒子と波動の両方の性質があるだって? マジ? しかも排他原理なんてものまで見つかっちゃって、えらい大変じゃんか。ボーアが一定の成功を収めたとはいえ、これでいよいよ、古い革袋にいつまでも頼っているわけにはいかなくなった。量子という新しいぶどう酒には、新しい革袋が必要だ。その革袋を、ついに発見したのが、ハイゼンベルクとシュレーディンガーだった。
彼らは、ほぼ同時に同じことを考えていた。着想を得たのはハイゼンベルクのほうが、わずかに早かったけど、研究を先に発表したのはシュレーディンガーだった。話はちょっとそれるけど、シュレーディンガーには勇気づけられる。ふつう、科学者が大発見をするのは、若いころと相場が決まっている。ところが、シュレーディンガーが、その後の物理学に大きな影響を及ぼす理論を考えたのは、なんと、三十八歳のときだった。ぼくより年上だ。なんか、うれしいね。そういえば、プランクが黒体輻射を説明したのも42才のときだったな。ラザフォードが原子核を発見したときは40才。ふーむ。オッサンも捨てたもんじゃないじゃんか。いや、ぼくは、断じてオッサンではないけど(笑)。
失礼。話を戻そう。
えーと、シュレーディンガーとハイゼンベルクのことだったね。アインシュタインとプランクが、量子論の幕開けだとしたら、この二人が第二幕の主役たちだ。
彼らは、いったいなにを考え出したのか? その説明をするために、ひとたびニュートンに戻ろう。ニュートンは、光を粒子だと考えた。そうすると、光が屈折したり反射したりする理由がうまく説明できたからだ。ところが、ニュートンの死後、約半世紀で、光は波だということが決定的になった。
でも、ニュートンの光学理論が、そのことで無用の長物になったわけじゃない。レンズを通る光や、鏡に反射する光を計算するのに、ふつうは光を波動と考えて複雑な計算をする必要はない。レンズの焦点を通過する光を、何本かの光線として描いたり、鏡に対して、そういう光線を描くときは、入射角と反射角が同じになるように反射させればいい。こういうのを幾何光学って呼ぶ。
ぜんぜん科学的な話じゃないけど、ぼくのような写真のプロは、光が反射するとき、入射角と反射角が等しいことを利用して、商品のライティングを決めたりするんだよ。たとえば、撮影したい商品なり人物なりを、どの角度から撮るか決まれば、必然的にカメラの位置も決まるよね。すると、そのカメラのレンズに入射する光は、商品に当てるライトの角度によって決まるわけだ。このとき、不適切な位置にライトを持ってきてしまうと、入射角=反射角の法則によって、商品はビカッ! と不必要に光りすぎちゃう。つまりカメラマンになるためには、幾何光学を学ぶ必要があるのであって…… って、商品撮影の方法を解説してどうする(笑)。まあ、実際には、商品の反射率も違うし、人間など形の複雑なものを撮影するから、この法則を常に遵守しているわけじゃないよ。念のため。
脱線しちゃった。ごめんね。
とにかく、光が当たっている物体が、光の波長よりずっと大きければ(たいてい大きい)、なにも小難しく光を波動と考えなくても、幾何光学で計算できるわけなんだよ。これは古典物理学で扱える光の粒子理論とほとんど変わらない。つまり、ニュートンが考えた光学理論は、まるっきり間違っているんじゃなくて、本来、光を扱うべき波動力学の「近似値」といえるんじゃないだろうか?
難しいかしら? うーん。もっと簡単に説明するにはどうしたらいいかな。よし。地図を考えてみよう。あなたは、来週パリに旅行することになったとしよう。もちろんはじめての旅行だ。そこで、パリの地図を手に入れた。大通りの名前や、建物の名前がいろいろ書いてある。あなたは、その地図を見ながら、来週行くパリの街を頭に思い描くことができるはずだ。でも、その地図は、もちろんパリそのものではない。幾何光学は、この「地図」に似ているかもしれない。本物ではないけど、本物を連想するにはことができる。
となれば、幾何光学から、本来あるべき「正しい理論(波動力学)」を類推することができるんじゃないだろうか? オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガーは、そのように考えるところからはじめてみたんだ。
こうして、1926年。シュレーディンガーは、波動力学を完成させた。ドイツの物理学者ウェルナー・ハイゼンベルクも、やや遅れてマトリックス力学として発表した。シュレーディンガーは37才だったけど、ハイゼンベルクはこのとき24才の血気盛んな若者だった。いまでこそ、両者の理論は似たような(それどころか同じもの)とか言ってるけど、これらが発表されたときは、別物だと考えられていた。しかし、このときこそ、「量子論」が「量子力学」として確立されたのだと、言っていいかもしれない。
それはそれとして、波動力学ができてみると、ボーアが、いかにその場しのぎで電子の動きを計算していたかがわかった。ボーアは、電子が原子核を回る軌道を、円軌道として考えたけど、じつは、そんなことはあり得ない。ボーアは、そのことを指摘されて、怒り出すどころか、むしろ喜んだ。彼は量子論が正しく適用されるべきだと考えていたからね。ときにボーアは41才になっていた。
さて。電子がボーアの考えたような円軌道をとらないとなると、波動力学やマトリックス力学では、どういう軌道をとるのだろう……
じつは(誤解を恐れずに言うなら)、それを説明することは不可能なんだ。電子は「ぼやっと広がっている」のであって、どこに、いつ、どのような動きで存在しているのかを知ることはできない。うーん。なんと説明したらいいだろう。とにかく「不可能」と考えること自体が重要であり、かつまったく新しい「考え方」だったんだよ。ラプラスが、未来の出来事はすべて計算できるなんて考えていたのを思い出してほしい。古典物理学を信じている人たちは、電子の位置も、その動きも、われわれが知ることは「可能」だと思っていんだ。ところが、この新理論を考察したマックス・ボルンは、新理論で説明されている「波動」は、そうした「決定論」ではなく、「確率」としてしか語れない波だと明らかにしたんだ。
いったい、どういうことだ? 物理学になにが起こっているんだ?
ここでハイゼンベルクは自問した。本当に電子の動きは「確率」でしか語れないのだろうか? 自分の理論で展開されている数式では、たしかにそうなんだけど、それは間違いなく現実の世界を表しているんだろうか? つまり、数学的見地からは正しく思えても、物理的見地から見たら正しいだろうか?
そこでハイゼンベルクは、実際に「電子」を観測するところを頭に思い描いた。
いまあなたは、電子の位置と運動量を正確に測定しようとしている。電子の位置を決定するには、電子に光を当てて顕微鏡で見て見つけ出せばいい。ところが、ご存じのとおり電子はものすごく小さいから、光の波長を短くしないと、顕微鏡で観察できるような像を結ぶことはできない。わかるよね? 光は波でもあるわけだから、その波の山と山の間には「距離」がある。観測する物体の位置を、この「距離」よりも細かく測定するためには、山と山の距離を短くしなきゃいけない。つまり、波長の短い光を使う必要があるってことだ。ところが波長を短くすれば、それにつれて量子のエネルギーも大きくなるから非常に困ったことが起こる。すでに、この辺から、わけわかんなーい。と首をひねる方もいるだろうけど、この点は、そういうもんなんだよと思って読んでくだされ。
さて。電子を観測するために、どんどん光の波長を短くしようじゃないか。古典物理学では、たしかにそれでよかった。ところが、量子力学では、いくらでも小さな量の光を使うわけにはいかないんだ。少なくとも、ひとつの量子を使わなくちゃダメだ。うーむ。これをどう説明しよう。まったく、頭を悩ますエッセイだな…… ボケ防止には最適だよ。ぶつぶつ……
失礼。つい独り言が。
量子力学では、光は「光子」として扱わなければならないといえばいいのかな。この場合、光の強さには最低値があって、それよりも小さくはできないんだ。すると、電子を観測しようと思って光子を当てると、電子に当たった光子が跳ね返って、顕微鏡のレンズに入ってくる。ここまではいいんだけど…… じつは、このとき顕微鏡のレンズに入ってくる光子の位置をコントロールできないんだ。
ダメだなあ。この説明でも、まだ難しいよね。よし、わかった。ではこう理解してくれればいい。とにかく、電子を観測するためには、光を当てなきゃいけない。でも、その光のほうが強力すぎて、電子に当たったとき、そいつをはね飛ばして、運動量を変えてしまうのだよ。だから、光子が電子に当たった瞬間の位置はわかるけど、そのあと電子がどうなったかは、サッパリわかりませーん。ということになってしまう。
この説明でいいや。うん。大丈夫、大丈夫。つぎ行こう。
では、電子の運動量を変えないように、弱い光を使おうじゃないか。そうすると、たしかに電子の運動量はわかるんだけど、上で説明したとおり、電子のほうが光の波長の山と山の間の距離より小さいから、位置がわかんない。
というわけで、われわれは、電子の位置か運動量かの、どちらかを測定することはできるけど、両方を同時に知ることはできないんだ。
ハイゼンベルクは、このように考えて論文を書いたんだけど、じつは顕微鏡の分解能は光の波長によるものだけではなくて、その口径の逆数にも依存している。彼の最初の原稿では、この点が考慮されていないことを、ボーアが指摘した。ボーアは量子力学のご意見番だったんだね。だからハイゼンベルクは、校正刷りの段階で、あわてて註釈として、その問題をつけ加えなくちゃならなかった。
これには、ちょこっとおもしろい逸話が残ってる。ハイゼンベルクは、この論文を作る少し前に、ミュンヘンで博士号をとろうとしていた。ところが、ハイゼンベルクは生意気な青年だったから、ウィーンという名前のジジイの実験物理学の教授に嫌われていた。当然ウィーンは、この小僧を不合格にしたかった。そこで、光学機器の分解能についてハイゼンベルクに質問した。ハイゼンベルクはその質問に答えられず、ウィーンはしてやったりと笑いながら、ハイゼンベルクを不合格にした。
すると、アルトゥール・ゾンマーフェルトという理論物理学の教授がぶったまげた。彼は、ハイゼンベルクの有能さを十分に理解していたから、博士号の試験に落ちるなんて考えられなかったんだ。そして、それがウィーンの嫌がらせだとわかると、すぐさまウィーンと話し合い、なんとか頭の固いクソジジイを説得して、ハイゼンベルクに博士号をとらせることに成功した。ただし、ウィーンの顔も立てて、ハイゼンベルグの成績は、博士号がとれる最低レベルだった。
ところが、のちにハイゼンベルクが書いた論文の不備は、まさにウィーンがついた、光学機器の分解能についての部分だったから、ハイゼンベルクは晩年に後悔の念を持って、ウィーンが、自分に博士号をとらせたくなかったのは当然だと発言している。もちろん、ゾンマーフェルトが、彼に博士号を与えたかったのも当然なんだけど。
このようなわけで、1927年(1926年としてる資料もある)。ハイゼンベルクは、新しい力学で提起した概念を、いよいよ決定的なものにするべく、かの有名な「不確定性原理」を発表したわけなんだ。いままで説明してきた、電子の位置と運動量の両方を同時に知ることができないというのは、まさに「ハイゼンベルクの不確定性原理」で述べられていることだったんだよ。
とにかく。不確定性原理は、われわれが世界を見る見方にとって、深刻な意味を持っている。いま現在の状況だって、満足に観測できないのに、ラプラスが夢想したような、未来の出来事を予測するなんてことができるだろうか? もちろん、答えはノーだ。古典物理学における「決定論」は、皮肉なことに「決定的」に崩壊した。
以上が、量子力学の第一の特性である「不確定性」についてだ。続きましては、量子の第二の特性である、「量子は通った道筋がわからない」という、これまた摩訶不思議な現象の話をしよう。
そのためにまずは、二重スリットと呼ばれる実験を見てみよう。もともと、この二重スリットは、量子力学が誕生するずっと以前に、トーマス・ヤングが光は波動であることを示すために行った実験だ。ここでついに、言葉だけで説明をするという、自らに課した掟を破って、図を投入することにしよう。(このエッセイのために、ぼくが自分で描いたことを、ぜひ強調しておきたい!)
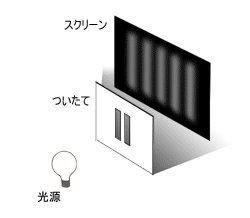 |
|---|
ご覧のように、電球(光源)があって、その向こうに、縦に穴が二つあいた「ついたて」がある。その後ろに黒いスクリーンが置いてある。この図は、電球のスイッチを入れて、光を当てたところだ。スクリーンに、縦長の縞模様ができているのにご注目いただきたい。(念のために申し上げておくと、この図はあくまでも概念図であって、あなたが段ボールで似たようなものを作って実験しても、こんな理想的な状態にはならない)
さて。しばらく量子力学は忘れて、ヤングの実験にだけ注目しよう。縦長の縞模様ができることがすなわち、光が波動であることを示している。どういうことかというと、光は、右側と左側の、それぞれの穴を通ってスクリーンに達するわけだけど、もし光が粒子ならば、スクリーンには、縦長の帯が二つできるだけのはずだ。わかるよね? たとえば、砂が詰まった箱を連想してほしい。その箱を持ち上げて、箱の底に穴を二つ開けたら、どうなるだろう。砂時計のように穴から落ちた砂は、床の上に二つの山を作るはずだ。けっして、複数の山を作ることはない。これは砂が「粒子」だからだ。
ところが、スクリーンには縞模様ができる。ヤングは、これこそ光が波である証拠だと考えた。波には山と谷がある。当然、右と左を通った光の波は互いに干渉しあう。つまり、その山と谷が完全にそろっていないと、ある場所では山と谷が強めあい、ある場所では弱めあうことになる。その結果、波の干渉によって、縞模様ができるわけだ。
ここまではオッケイかな? では、この実験を量子力学の面から見てみよう。
光の代わりに、こんどは電子を使おう。しかも、電子を砂のように降り注ぐのではなくて、たった一個の電子を、ついたてに向かって撃ち込むことしよう。一個打ち込んだら、少し間を開けて、また一個撃ち込む。これを何百回と繰り返すんだ。
さあ、みんな。結果はどうなると思う?
当然、電子は粒子としてついたてに撃ち込まれているのだから、どちらかの穴を通って、スクリーンに当たるよね。つぎの電子も、どちらかの穴を通って、スクリーンに当たる。だから、光の干渉でできたような縞模様はできない。
と、思うんだけど、ところが、なぜか縞模様ができるんだ。では、「電子」も波なんだろうか? そうかもしれない。でも待ってくれ。ぼくらは、電子を「一個ずつ」しか撃ち込んでいないんだよ。一個しか電子が飛んでいないはずだから、べつの電子と干渉するはずがないじゃないか!
と、鼻息荒く反論しても、干渉ができるんだからしょうがないじゃんか。それは事実なんだから。だから、事実に合わせて「考え方」のほうを変えよう。
一個ずつ撃ち込んだ電子が干渉を起こすためには、その一個の電子が、同時に二つの穴を通り抜ける必要がある。とても信じられないことだけど、分割不可能な電子が、なんらかのマジックで、二つの穴を当時に通り抜けたんだ! こんな現象は古典物理学では考えられない。ところが量子力学の世界では起こるんだよ。
しかしだね。こんな不思議な現象をほっておくのは気分が悪い。穴のとなりに電子を検知する装置を取り付けて、電子が通ったとき、電球が光って電子を照らすように装置を改良しよう。こうすれば、本当に分割して二つの穴を同時に通ったのか調べられる。
ところが……
その観測をはじめると、電子は分割なんかしないで、お行儀よく、どちらかの穴を通っているだけなのだった。当然、干渉は消え、縞模様は現れなくなる。
おかしいな。もう一度、電子の検出器を切って、最初の方法で実験しよう。すると縞模様が現れる。あれ? では検出器のスイッチを入れよう。すると縞模様が消える。
なんでー! 人が見ているときには、行儀よく、どちらかの穴しか通らないくせに、人が見ていないと、とたんに幽霊みたいに分割して、二つの穴を同時に通るようになるなんて! 電子に化かされているとしか思えない!
そう。われわれは電子に化かされている。彼らの本当の姿を直接見ることは絶対に出来なんだ。検知器を作動させた時点で、ハイゼンベルクが不確定性原理で考えたとおり、電子の振る舞いが変わってしまうんだよ。つまりぼくらは、電子が通った跡を見て、確率的にしか電子の動きを把握することが出来なんだ。
ところで、あまりにも量子力学の概念が理解しにくいので、シュレーディンガーは1935年に「シュレーディンガーの猫」というパラドックスを考え出した。ごく簡単に説明すると、ウラン原子が崩壊するのを検知するガイガーカウンターを置いた箱に、毒ガスのビンと猫を入れておく。ガイガーカウンターが、ウラン原子の崩壊を検知したら、毒ガスのビンが開いて、哀れな猫ちゃんが死んでしまう。では、猫ちゃんが死んでしまう確率はいかなるものであろうか?
答え。死ぬかもしれないし、死なないかもしれない。つまり、どっちもどっち。箱を開けてみなければ、結果はだれにもわからない。なぜかというと、ウラン原子の崩壊は、半減期という、全体の半分が崩壊する期間を確率として言い表せるけど、いつ、崩壊するかという決定的なことは言えないんだ。一秒後かもしれないし、あるいは一万年後かもしれない。それはだれにもわからない。量子力学では、そのような状態のとき「死んでいる猫と生きている猫」が同時に存在すると考える。古典物理学では、違った二つの状態が同時に存在するなんてパラドックスであるけど、量子力学では、パラドックスだとは考えないんだ。
以上、見てきたように、もはや電子は「波である」とか「粒子である」とかいう言い方は、あまり適切ではなくなってきた。「あらゆる経路を通る可能性のある量子」と呼ぶのがよさそうだ。それによって、「波動でもあり粒子でもある」という特性を説明していることになる(二重性というんだけどね)。だから、波として扱ったほうが計算が楽な場合はそうすればいいし、粒子として扱ったほうが計算が楽な場合はそうすればいい。それらは近似値ではあるけど、十分に使える答えが求められる。
そのことを正確に証明したのが、イギリスの物理学者ポール・エイドリアン・モーリス・ディラックだった。
彼は1927年に、光を粒子として扱えばそうなるし、波として扱えばそうなるってことを、数学的にキチンと示したんだ。なんとディラックはその数式に、相対論の考え方を取り入れた。物理学の二大理論に整合する数式を作り出したのは、ディラックがはじめてだった。彼の理論からは、電子にはパートナーとなる粒子があるはずだと予想できた。そのパートナーは、電子とはまったく逆の電荷を持っているはずだった。反電子、すなわち陽電子だ。それどころか、すべての粒子は反粒子を持っているはずだった。もちろん、理論どおり反粒子が見つかったので、ディラックはノーベル賞をもらった。
これで終わった。物理学者は安堵した。1925年から1927年にかけて、どどどどーっと、津波のように量子力学は大きく前進したんだ。1928年。のちにノーベル賞を受けたマックス・ボルンは、ゲッティンゲン大学を訪れた人たちに向かってこう言った。「わたしたちが知っている物理学は、もう六ヶ月もすれば完成ですよ」と。ディラックが電子に関する理論を完成させて、謎がすべて解明されたと思ったんだ。
とんでもない!
物理学は、これからのちも、さらに新しい謎に直面する。と、その話をする前に、またアインシュタインに登場願おう。
大成功を納めつつある量子力学に異を唱える科学者がいた。しかも超大物がだ。そう。アインシュタインだよ。
アインシュタインは、どうしてもハイゼンベルクの不確定性原理が気に食わなかった。そんなものを認めれば、物理学が崩壊しかねないとさえ思った。彼は「神はサイコロを振らない」という言葉で、自分の気持ちを表した。そう。この世の自然現象は、サイコロを振るような確率論ではなく、決定論で語れると言ったんだ。おいおい、アインシュタインともあろうものが……
この超大物を、なんとか量子論の世界になじませようと奮闘したのは、量子論のご意見番ニールス・ボーアだった。ボーアは、相補性原理を1927年に発表した。たとえば、素粒子のような、むちゃくちゃ小さいものを対象にするときは、波動的な表現と粒子的な表現とが共に欠かせない組として必要だってことを、まあ、改めて概念としてまとめあげたんだ。
こうして、アインシュタインとボーアの激論がはじまった。なかでも有名なのが、1930年にブリュッセルで開かれた、第6回ソルヴェイ会議。ここには、キュリー夫人をはじめ、当時、世界第一級の科学者が集まった。すごいねえ。
口火を切ったのはアインシュタインだった。アインシュタインは、ちょっとした思考実験のための装置を考案した。それはバネによって吊り下げられた箱だった。さらに箱の中に光源があって、そこから「光子」が箱の外に飛び出る仕組みになっていた。この装置を使って、アインシュタインは、不確定性原理を攻撃した。
「いいかね、ボーア博士。箱の中の電球から発した、ひとつの光の粒が、シャッターを通って箱の外に出るとしよう。すると、シャッターに連動した正確な時計で、光の粒が、いつ外に飛び出したのかその時間を知ることができる。一方、箱は光の粒一個分だけ軽くなる。すると箱を吊り下げているバネが縮んで、重さの変化がわかる。そこから光の粒一個分のエネルギーを計算することができる。ご理解いただけるかね、ボーア博士。われわれは、時間とエネルギーの両方を、同時に測ることができるのだよ。ところが、きみんとこの若いもんが考えた『不確定性原理』とやらでは、それができないと述べているそうじゃないか。違うかね?」
まあ、実際は、こんな高圧的な態度じゃなかったろうけど、アインシュタインはいつも自信満々だから、気分的にはこんな感じだったろう。
これに対して、ボーアはどう反応したと思う?
なんと、答えられなかったんだ! さすがアインシュタイン。ボーアなんか目じゃないぜ。アインシュタインは、にんまり勝ち誇った笑顔を見せ、ボーアは不機嫌そうに、その場を去った。この日、ボーアは一日中不機嫌で、会う人会う人に、「もしも、アインシュタインが正しければ、物理学は、もうおしまいだ!」と言って回ったそうだ。
ボーアは、その晩。アインシュタインの理屈をじっくり考えてみた。どうもなにか引っかかる。もしも、宇宙空間に彼の言う箱があったら…… 重力が……
ん? 重力? 待てよ。そうか! わかった!
ボーアはなんと、その晩のうちに、アインシュタインへの反論を思いついた。翌日の会議で、ボーアの反撃がはじまった。
「アインシュタイン博士。昨日は見事な弁論に打ち負かされましたが、一晩考えまして、わたしは、あなたの重大な誤りを発見しました。あなたの想定したバネばかりは、重力の中にあります。となれば、軽くなって箱が動けば、相対性理論によって時間は遅れるはずなのです。つまり、時間は正確に測れないのですよ。よろしいですか博士。この誤りはあなたの偉大な発見である相対論に根ざしているのです!」
ガーン!
アインシュタインは大ショックを受けた。あわてて考えてみたが、ボーアの言うとおりだった。アインシュタインは自分の理論によって、自分の誤りを指摘されちゃったのだ。翌年に発表した論文では、ボーアの見解の正しさを認めてさえいる。その痛手から立ち直った1935年に、若い二人の研究者とともに、もう一度量子力学のパラドックスを指摘した。このときのボーアは動じなかった。すでに、古典的な測定装置の置かれた状態を無視して、量子力学的系だけを論じてはいけないと確信していたんだ。じっさい、アインシュタインと若い研究者が提起したパラドックスるは、量子力学を根底から揺るがすよなものではなかった。それでもアインシュタインは、生涯、不確定性原理に疑問を持ち続けた。誤解のないように言っとくけど、べつに量子力学が間違っていると思っていたわけではなくて、「不完全」だと思っていたんだ。そして、相対論の不完全さも、量子力学の不完全さも、どちらも解決できる理論があるはずだと信じて研究を続けた。
さて。こんどは、アインシュタインと、彼が忌み嫌った不確定性原理を考え出したハイゼンベルクの話をしよう。この二人は、まったく違う世界観を持っていたにもかかわらず、けっこう似ている。二人ともドイツ出身だし、どちらも、それまで人々に信じられていた理論をぶち壊した偶像破壊者だ。アインシュタインが相対論でそれをやったのは26才のときで、ハイゼンベルクが不確定性原理を発表したのは24才だった。
ところが。彼らの運命は、第二次世界大戦によって、その理論と同じくらい百八十度変わってしまう。アインシュタインは、ナチスから逃れてアメリカに渡ったけど、ハイゼンベルクはドイツに残って…… なんとヒトラーの原爆計画に従事した。
じつは、アインシュタインが、フランクリン・ルーズベルト大統領に、アメリカによる原爆計画を進めるように進言する手紙を書くのを、他の科学者から迫られたのは、ドイツにハイゼンベルクという、超一流の科学者がいたからなんだ。アインシュタインは苦悩した挙げ句、ついに平和主義を捨てて、その手紙を書いた。こうして、1939年8月、日本では悪名高い(アメリカではそうでもないらしい)「マンハッタン計画」がはじまった。
なぜアメリカはドイツより早く原子爆弾を作ることができたのだろうか。それどころか、当時、二十年はかかるといわれた原爆の製造を、アメリカはわずか数年で完了してしまった。なぜ、そんなことが可能だったのか?
じつは、ナチスから逃れた科学者はアインシュタインだけではなかったんだ。なんと二千に近い科学者がドイツから流出したらしい。そして、ノーベル賞をもらった科学者たちが、ぞくぞくと、ロス・アラモス研究所に集まった。計画の中心人物は、ジョン・ロバート・オッペンハイマーだった。エンリコ・フェルミもいた。ボーアも、ファインマンもいた。エミリオ・セグレもいた。アーサー・ホリー・コンプトンもいた。とにかく、すでにノーベル賞をもらっているか、後にもらうことになる頭脳が大結集したんだ。ドイツ側には、ウランに中性子照射すると核分裂が起ることを発見した、オットー・ハーンと、ハイゼンベルクがいたけど、第一級の頭脳はこの二人ぐらいのものだった。
そして、ドイツは降伏した。ところが、まだ戦っている国があった。原爆は、その有色人種の国に落とされた。アインシュタインは、その報を聞いて悲願にくれた。そして、記者会見の場で「おそろしい……」と、ひとこと言ったきり絶句して、あとはなにも語らなかった。
余談だけど、原爆の父なんて呼ばれているオッペンハイマーは、後に、水爆の製造に反対して、原子力委員会顧問の座から追放された。みんな作りたくはなかったんだよ。あんなもんは。
いかん。また話が脱線気味。ぼく自身、このエッセイが宇宙の秘密について語っているのを忘れてるね。では、本題に戻ろう。
前回のエッセイ(宇宙の秘密その2)で、ぼくはアインシュタインがすべての「力」を統一した統一場理論を追い求め、けっきょく、その理論を完成させることなくこの世を去ったと書いた。もしかしてアインシュタインは、量子力学の不確定性原理という、素粒子の世界での「事実」を認めることができなかったから、統一場理論を完成させられなかったのだろうか?
そうかもしれない。少なくとも原因のひとつではあっただろう。だからこそ、特殊相対論と量子力学を結合させることができたのは、アインシュタインでなかったのも驚くに当たらない。それをやってのけたのは、アメリカの物理学者リチャード・ファインマンだ。彼は、原爆を造っていたロス・アラモス研究所時代に、その仕事をしている。
ファインマンは、じつはどうしても、シュレーディンガーやハイゼンベルクの理論を理解できないでいた。そこで、イタズラ好きで陽気なファインマンは、ハイゼンベルクたちの小難しい数式を使わない、もっと簡単に計算する方法を考え出した。
ここで、さきほど説明した二重スリット実験を思い出そう。ファインマンは、「電子の道筋がわからない」のではなくて、「電子はすべての道筋を通る可能性がある」と考えたんだ。つまり、右の穴を通る可能性と、左の穴を通る可能性を足してやらなければならないんだ。でも、穴がもっと多かったらどうなる? その場合は足し算ではなくて積分しないといけない。だから、ファインマンの考えた、あらゆる可能性を積分する方法を「経路積分」と呼んでいる。この方法で、シュレーディンガー方程式を使わずに、ずっと簡単に「同じ答え」が得られることがわかっている。
ファインマンはさらに進んで、1949年に特殊相対論と量子力学を結合させて、量子電磁力学という名の理論を作り出した。1930年にオッペンハイマーが、量子力学を特殊相対論と結合させると、電子のもともとの(裸の)質量と電荷に無意味な無限大が出てくると予想していた。無限大は理論にとっては癌みたいなもので、無限大がある限り、どんな理論も死に至る。つまり、世に認められることは絶対にないんだ。
ファインマンは、いまでは「ファインマン・ダイアグラム」と呼ばれる手法を考え出して、この問題に挑戦した。彼は、面倒な数式を飛び越して、直感的に無限大を除去しちゃったんだ。むちゃむちゃ簡単に言うと、ファインマン・ダイアグラムとは、数式を図形として視覚的に理解する方法だ。無限の除去は、ハーバード大学のジュリアン・シュウィンガーや、東京大学の朝永振一郎も公式化していた。シュウィンガーと朝永のほうは、怪しげな図形なんかじゃなくて、正統的な数学だった。
そりゃそうと、無限大を消し去る方法とは、どんなものなんだろう? これもむちゃくちゃ簡単に言うと、無限大から無限大を引き算しちゃうんだ。これを「繰り込み」という。でも、そんなバカなことがあるんだろうか? ∞−∞=0なんてことが、数学的に許されるのか?
当然、彼らの理論は懐疑的に見られた。あのディラックでさえ、「そんなバカなことあるか」と憤慨した。ところがどっこい、この理論は、とんでもなく正確に実験結果と一致するんだ。というわけで、ファインマンの理論が、朝永たちの理論と同じものだと証明されたのち、彼らは仲良く1965年にノーベル賞をもらった。
繰り込みという手法によって、量子力学はまた前進した。ところが、状況は、またまた複雑になってしまった。
1935年。湯川秀樹が中間子理論を発表した。これは、原子核の中で陽子を結びつけているのは、いったいなんだろうと考えてできた理論だ。俗に、強い力と呼ばれることになる「強い相互作用(強い核力)」の発見の起源と言える。
そう。われわれは原子核の中でだけ作用する、新しい「力」を発見してしまったんだよ。この強い力だけでなく、電子などの軽い粒子に作用する、「弱い相互作用(弱い核力)」があることもわかった。
では「強い核力」と「弱い核力」の話をしよう。
まず「強い核力」だけど、これは陽子とか中性子とか、まあ単純に言うと素粒子のなかでも大きな粒子をくっつけてる力だ。弱い核力は、電子などの小さな粒子に作用する。これらの力は、どうやって伝わるんだろう? じつは、力を伝える粒子があるはずなんだよ。たとえば弱い核力は、W粒子とかZ粒子を互いに交換することで作用が生まれる。強い核力はグルーオンと呼ばれる粒子が担っている。
この「粒子の交換で力を伝える」という新しい考え方を最初に提唱した人物こそ、日本の誇る湯川秀樹だ。彼の考え方は、強い核力だけでなく、弱い核力、そして電磁気力の引力にまで拡張された。たとえば、電磁気の引力の場合は、スピン1で質量のない仮想的な光子を大量に交換することで生じると考えられている。このとき交換される粒子は、けっして観測できない。表にはでてこないんだ。だから「仮想粒子」と呼ばれている。「観測」できないのに、それが「ある」と主張するのには無理があるかもしれないけど、この理論は、とてもよく素粒子の振る舞いを説明するし、仮想粒子の存在を示唆する現象を観測することで、物理学者たちは「ある」と信じている。アインシュタインが生きていたら反対するかもしれないけど、きっとあるんだろう。
アインシュタインが、この世を去ったのは1955年。核力が研究されはじめたころには、すでに老人であり、亡くなったのは、核力の研究がやっと本格的になってくるところだった。つまり彼は、この新しく発見された「力」のことを、ほとんどなにも知らない状態で、統一場理論を考えていたんだ。それじゃあ、いくら天才でも完成するわけがない。
では、かなり核力の研究が進んだ現代ではどうだろう? 電気と磁気、そして光は電磁気力として統合できた。核力は統合できないだろうか?
1967年。弱い核力と電磁気力の統合が実現した。その理論を提唱したのはロンドン大学のアブダス・サラムと、ハーヴァード大学のスティーヴン・ワインバーグの二人だった。ワインバーグ=サラム理論では、エネルギーが100ギガ電子ボルトをはるかに超えると、新しい粒子と光は、すべて似たような振る舞いを示すようになる。
このことを簡単に言うと…… うーむ。ルーレットを思い浮かべてみよう。ルーレットの盤が回転しているとき、中にある玉は、ただひたすらグルグル回っているだけだ。これが高エネルギー状態。ところが、盤の回転が遅くなると、玉はどこかのくぼみに落ちていこうとする。最終的に盤が止まると、玉は三十七個ある数字の穴の、どこかに落ちる。このとき、玉には落ちた場所の番号が与えられるわけだ。これが低エネルギー状態。わかるかな? 盤が回っているとき、玉はまだ「何者でもない」。ところが、低エネルギーになると、玉には「番号がつく」。これと似たようなことが、素粒子の世界にはあるんだ。高エネルギーのときは、みんな同じに見えるんだけど、低エネルギー状態では、それらの素粒子は、「別のもの」に見えちゃうんだよ。
つまり、高エネルギーの状態では、弱い力を伝える粒子は、光子と似たような振る舞いをするように見えちゃうんだ。ということは、結局のところ、弱い力は光と同じなんじゃないのか?
この理論を二人が提唱したとき信じた人は少なかったけど(新しい理論は、いつだってそうだ)、その後、約十年かかって彼らの理論が正しいという証拠がそろってきたので、サラムとワインバーグは1979年にノーベル賞を受賞した(もう一人、似たような理論を提唱した、シェルドン・グラショウも同時に受賞した)。彼らの成功の鍵は、マックスウェルもビックリするようなゲージ対称性にあった。当時もっとも洗練されていた、ヤン−ミルズ理論を使って…… なんて書くと、いよいよ複雑になっちゃうなあ。いいや。そのへんの説明は省略しちゃおう。(対称性については、説明しなきゃいけないような気もするけど、その誘惑には打ち勝とう)
続いて、強い核力にも科学者は取り組んだ。これは、さっきも書いたけどグルーオンという粒子が担っている。グルーオンが「ひも」のような役割をして、クォークをくっつけているんだ。グルーオンは自分自身と、陽子や中性子を構成しているクォークとしか相互作用しない。
あ、ちなみに陽子と中性子は「クォーク」と呼ばれるものでできている。ちょっとクォークの話しもしておこう。
1950年から1960年にかけて、物理学者たちは、強い相互作用をする粒子を何百種類も発見した。これらはそれぞれに質量の違う粒子なので、別のものなのは間違いない。いまでは総称して「ハドロン」と呼ばれている(陽子や中性子などを含む)。自然が単純な法則で作られているなら、素粒子は数が少なくなければならないのに、実際はその逆になってしまった。どうやら、またまた新しい理論でこの状況を整理する必要があるように思われた。エンリコ・フェルミは、ハドロンの大量生産に、こう嘆いたそうだ。「こんなにたくさんの粒子の名前を覚えられるくらいなら、植物学者にだってなれたはずだ」と。さらに、オッペンハイマーは、「ノーベル賞はその年に新たな粒子を『発見しなかった者』に与えるべきだ」。なんて冗談まで言っている。それほど、ハドロンが、じゃんじゃか発見されていったんだ。
いったい、なぜこんなに新しい粒子が発見されるのか? その粒子たちに、なにか共通点はないのか? そこで科学者たちは、もっと「基本的な要素」である、クォークを考え出した。クォークの組み合わせで、数百種類も発見されたハドロンがうまく説明できるんだ。なぜ質量が違って見えるのかは、そのハドロンの中にあるクォークのエネルギー状態の違いと説明できる。アインシュタインのE=mc2を思い出そう。エネルギーと質量は等価だから、エネルギー状態が違うと、質量の違いとして観測されるってわけなのさ。
こころで、クォークという名前の由来なんだけど、こいつは自然科学には珍しくギリシア語やラテン語じゃないんだ。「ユリシーズ」で有名なジェームズ・ジェイスって作家を知ってる? 彼の作品の中に「マーク大将のために三つのクォークを!」という謎めいたセリフがあって、クォークが考えられた当時、ちょうどクォークは三つだと思われていたことから、この名前が付いたんだ。命名したのは、カリフォルニア工科大学のマレー・ゲル=マンだった。彼はクォークの研究で1969年にノーベル賞をもらった。
強い核力に戻ろう。
クォークには「閉じ込め」という奇妙な性質がある。けっして単独では取り出せないんだ。常に組み合わせでしか存在できない。それを「色」という概念で理解しているわけなんだけど、まあ、ここで光の三原色を説明するのはしんどいから、そういうもんなんだと思ってくれればいいや。光の三原色を知っている方のために、ちょこっとだけ説明すると、クォークは、常に「白」になるような組み合わせでしか存在できないんだよ。「赤+緑+青=白」って具合さ。あとは三原色とははずれるけど、「赤+反赤」などの組み合わせもあり得る。それはクォークと反クォークを意味する。この場合は、中間子が作られるんだけど、クォークと反クォークは互いに消滅しあってしまうから、中間子はきわめて不安定なんだ。
さて。強い核力を担うグルーオンにも「色」があって、閉じ込めによって、単独では取り出せない。では、なぜそれらが存在すると証明できるんだろう? 仮想粒子のところで書いたけど、存在すると仮定しなければ説明できない現象があって、その現象を観測することで、存在を証明しているんだ。なんとなく形而上学的に思えるけど、まあ、間違いなく存在しているだろう。
弱い核力と電磁気力が統合されたのに刺激されて、強い核力と電磁気力を統合する理論も、大いに研究された。それは「大統一場理論」と呼ばれた。もちろんこれは誇大広告だ。重力が含まれていないのだから、大と名乗る資格はない。そしてそれは、完成されているとはいえない状況なんだ。われわれは、まだ強い核力のところでつまずいているんだ。
でもまあ、かなり、よさそうな理論はある。
方法としては、弱い核力を統合したときに使ったのと、同じ考え方を応用してみることだった。弱い力を伝える粒子は、高エネルギー状態では、光と同じものだと考えることができた。ではでは、強い力を伝えるグルーオンも、もっと高いエネルギーの状態だったら、光と同じなんじゃないのか?
科学者は、きっとそうだと信じている。では、実験して確かめてみればいいじゃないかと思うだろうけど、そう簡単じゃなんだ。グルーオンまでもが、統合されるような高エネルギー状態を作り出す実験装置を、われわれは持っていないんだよ。しかも、近い将来どころか、かなり遠い未来でさえ、そういう装置が作られる可能性はほとんどない。
なぜかというと、グルーオンまで統一できる高エネルギーの粒子加速器を作るとすると、その装置の大きさは、たぶん…… 太陽系と同じくらいになるだろうと予想されている。そんなもの、人間が作れるわけがない。地球と同じ大きさだって、きっと無理だろうに、太陽系と同じだなんて、建設費を計算する気も失せるほど途方もなさすぎる。
では、実験ではなく「観測」ではどうだろう? 大統一理論で予想される結果から、なにか観測できないだろうか? じつはある。われわれは「陽子」は安定していると考えていたけれども、大統一理論では、陽子は必ずしも永遠不変のものではないんだ。寿命がある。この理論が考えるエネルギー状態では、クォークと反電子に本質的な違いはなくなるからなんだ。だから、もしもクォークが反電子に変わったら、陽子は崩壊するはずだ。陽子の中にあるクォークは、ふつう反電子に変わるのに十分なエネルギーを持っていないけど、不確定性原理によって、そのクォークのエネルギーは厳密に固定されているわけではないから、ごく稀に、クォークが反電子に変わっちゃうこともあり得るってこと。そこを観測すればいいわけだ!
もちろん、科学者は観測をはじめた。
その装置こそが、わが日本が誇る「スーパーカミオカンデ」だ。じゃーん。この間ノーベル賞を受賞した、小柴昌俊が率いて作った実験装置だよ。
おや? 王立スウェーデン科学アカデミーが発表した小柴博士の受賞理由は、「天体物理学、とくに宇宙ニュートリノ検出への貢献」なんじゃないの? と、思ったあなた。新聞をよく読んでいらっしゃる。そう。たしかに宇宙から降り注ぐニュートリノを観測するためにカミオカンデはある。じっさい、1987年2月に、宇宙から飛んできたニュートリノをとらえることに成功した。
その後、小柴昌俊の後を引き継いだグループが、1996年に、蓄えておく水の容積を10倍にして、装置を大きくパワーアップし、スーパーカミオカンデと名前を変えたんだ。うーむ。それにしてもいつ書いてもカッコいい名前だ。スーパーカミオカンデ。そそるなあ(笑)。
失礼。雑念が(笑)。このスーパーカミオカンデは、陽子の崩壊も観測できるはずなんだよ。大統一場理論では、中に入っている水の分子の(そして原子の、さらに原子核の)陽子が崩壊するときに、K中間子とニュートリノが出てくるはずなんだ。ニュートリノを観測できるスーパーカミオカンデなら、このとき飛び出たニュートリノを捕らえることができる!
さて…… カミオカンデ(そして、スーパーカミオカンデ)が作られて、そろそろ二十年。この間に、陽子の崩壊は観測されただろうか? 残念ながら、答えはノーだ。一番簡単な統一場理論が予測するよりかは、はるかに陽子の崩壊は「起こりにくい」と証明しただけなんだよ(つまり、その簡単な理論は、間違っていたわけだ)。もしも、スーパーカミオカンデで陽子の崩壊を観測できたら、そのときは、また日本の科学者がノーベル賞をもらえるかもしれない。
というわけで、まだ大統一場理論は机の上の空論にすぎないんだ。証明されていないし、だいいち完全ですらない。なぜまったくソックリの粒子族が三つも(電子、ミューオン、タウ粒子だよ)あるのかを説明できていないし、任意の定数が多すぎるのも問題だ。もっと洗練された理論はないものだろうか? いや、それどころか、いまだに強情を張っている「重力」さえも統合できる、真の意味の大統一場理論は作れないものだろうか?
話は前後するけど、一時期、その候補として上がったのが「超弦理論」と呼ばれるものだった。これは「超ひも理論」とも呼ばれている。
この理論の、そもそものはじまりは、1968年のことだった。この年、ジュネーブ郊外にある、ヨーロッパ合同原子核研究所(CERN←セルンと読む)で別々の研究をしていた、二人の若い物理学者ガブリエル・ヴェネツィアーノと鈴木眞彦が、妙なことを考え出したのがキッカケだった。
詳しい説明は省くけど、当時、カリフォルニア大学バークレー校の、ジェフリー・チュウが考えたS−マトリックス理論(いわゆるS−マトリックスとは別物だけど)が流行していて、こいつがうまく機能するなら、いっそのこと、概念の論理的な展開じゃなくて、数学からその答えを推測しちゃえばいいじゃないかと考えた。そこで彼らは、十八世紀の以来、数学者たちが目録を作っている関数表に目を通した。そして彼らは、1700年代に活躍した、スイスの数学者レオンハルト・オイラーが最初に提示したベータ関数という式に注目した。調べてみると、チュウが提唱したS−マトリックス理論の公理のほとんどすべてが、ベータ関数で自動的に満たされることがわかった。
ビックリ!
二十世紀に発見された、強い核力の深い謎が、大昔の数学者が考えた関数で説明できるって? まさか! とは思うけど、かのニールス・ボーアが「新しい理論は、十分にキチガイじみていなければならない」なんて言ってるとおり、このキチガイじみた考えに、大勢の科学者が飛びついた。
なかでも、シカゴ大学の南部陽一郎が、ベータ関数は相互作用する「弦」の特性として説明できることを明らかにしたのは大きな前進だった。南部の理論を、プリンストンにいたジョン・ショワーツ、アンドレ・ヌボーと、アメリカの国立加速器研究所にいた、ピエール・ラモンらの理論に適用して、のちに「超弦理論」と呼ばれるものの基礎が誕生した。
ちなみに、南部は「質量」が生まれる理由も考え出したけど、こちらは質量ゼロの粒子も同時に誕生してしまう理論だったので、うまくいかなかった。
とにかく、この理論はもてはやされた。多くの論文が発表され、超弦理論を解説する一般書も多く出回った。(じつは、専門家でないぼくでさえ、超弦理論が大騒ぎされていたときのことを、うっすらと覚えているぐらいだ)
超弦理論は、大成功を納めそうな気配だったけど、残念ながら、そうはならなかった。なんと、この理論が成立するのは「26次元」と「10次元」だけだったんだ。
10次元だって? なんじゃそれは?
アインシュタインが提唱した、四次元って世界でさえ、最初は受け入れられなかったのに、10次元なんてものが、簡単に信じられるだろうか? この宇宙のどこに、10次元なんてものがあるんだ?
四次元なら、まだ理解できる。たとえば、ぼくが麗しい女性に出会ったとしよう。彼女のことを、美しい鼻すじを持ったとか、薄い唇が魅力的なんて思えるのは、ぼくも彼女も三次元という空間に住んでいるからだ。つまり、彼女を立体に見ることができる。そして、彼女が十年前に、少女だったころのことを思い浮かべることができたり、十年後に、いまよりさらに大人の魅力を持った女性になるだろうと想像できたりするのは、時間という概念を知っているからだ。三次元に、この時間を足して、ぼくらは四次元にいると言うこともできる。
でも、10次元ってのは、いくらなんでも、やりすぎだ。しかも、この理論が、光よりも速い「タキオン粒子」を予測しているように見えたのは致命的だった。そんなものが存在したら、タイムマシンが作れる。(拙作の恋愛小説『ラバーズ』を書く少し前に、超弦理論の解説書を読んでいたことを、ここに告白しよう)
こうして、1974年ごろには、超弦理論は、科学理論ではなくSFとして扱われるようになり、科学の舞台から消えた。まるで花火だね。打ち上げは華々しく、夜空にパッと咲いたけど、消えるのも早かった。
とはいえ、超弦理論の考察が、すべて無駄になったわけではない。超弦理論に含まれる考察のいくつかは、観測できる現象をうまく説明できそうだったから、すべてを捨てるのは、あまりにももったいなかった。たとえば、弦(ストリング)という概念で、クォークの閉じ込めを説明できたりする。だから、超弦理論は、細切れにされて、さまざまな理論に組み込まれていった。それでも、親である、超弦理論そのものに立ち戻ろうとする科学者は、あまりいない。
とはいえ、また超弦理論が完全復活しないとは言いきれない。それどころか、エーテルまでもが(もちろん十九世紀のエーテルとは違うけど)復活するかもしれない。
というのは、現代の物理学は、素粒子の質量を「ヒッグス場」として考えているからなんだ。こいつは、南部陽一郎の考えた質量の生まれる理由を、ヒッグスとキャップが改良して生まれた理論だ。ここで、ニュートンの「慣性」を思い出してほしい。慣性とは、加速に対抗する抵抗のことだった。つまり、動きにくさだ。素粒子に、「動きにくさ」を与えるような場がないだろうか。そういうものを想定できれば、重力もいよいよ量子化できるかもしれない。たとえばそう、プールの水のように。われわれがプールに入って歩こうとすると、水の抵抗で遅くなる。そういう「場」が、宇宙にまんべんなく広がってはいないだろうか? ようするにそれは…… そう「エーテル」ではないのか?
重力は、エーテルで伝わるだって? おいおい、またかよ。だったら、光はどうなるんだよ。秒速三十万キロメートルですっ飛ぶ光が、エーテルの中を伝播すると考えるには、どれほどの矛盾を抱え込まなきゃいけなかったと思ってるんだ。
そのとおり。ところが、科学者は、この新しい「エーテル」は、光とは相互作用しないと考えている。ホント? それってコジツケじゃないの?
さあ? それはわからない。量子重力論が完成した暁には、ヒッグス場の謎も解けるだろう。違うな。その謎が解けなければ、重力を量子化することはできないだろう。
というわけで、本当の意味での統一場理論はまだ完成していない。われわれは、永遠に統一的な理論を手に入れることはできないのだろうか。それとも、いまの状況は十九世紀の物理学者が、エーテルと格闘していたのと同じなのだろうか。もしそうだとすると、いつか天才が現れて、われわれの概念に革命をもたらしてくれるのだろうか。現代の物理学は、高度に専門化されているから、ひとりの天才が、すべてを解決することは不可能かもしれない。おそらく、いくつかの研究グループが合同で、少しずつ前進するというスタイルだろう。でも、ニュートンやマックスウェル、そしてアインシュタインのような、たったひとりの天才が、宇宙を見る目を、ガラリと変えちゃうなんて気持ちいいじゃん。ぼくは、そうなってほしいと思っている。加えて、ごく軽いナショナリズムから言って、それが日本人だったら、うれしいとも思う。
もし、そういう天才がいるとしたら、その天才は、いままさに、研究の最中なんだろうか。それとも、まだ生まれてもいないのだろうか?
それこそ、だれにもわからない……
Copyright © TERU All Rights Reserved.